

情報共有ツール「Scrapbox」が「Helpfeel Cosense(ヘルプフィール コセンス)」へと名称変更されてから、すでに半年以上が経過しました。発表当時は、多くのユーザー、特に長年Scrapboxを愛用してきた個人ユーザーの間で、不安や戸惑いの声が上がりました。私もその一人です。
このブログでは、名称変更から半年以上経った今だからこそ、改めて「Helpfeel Cosense」への移行が個人ユーザーに与えた影響について、深掘りして考察します。特に、「個人利用のハードルが高くなったように見える」という当初の懸念は、現状ではどうなっているのか。さらに、NotionやObsidianといった他のナレッジ管理ツールとの比較を通して、Cosenseの立ち位置と独自性を明らかにします。そして、個人ユーザーとCosenseのこれからについて、私なりの考えを述べたいと思います。
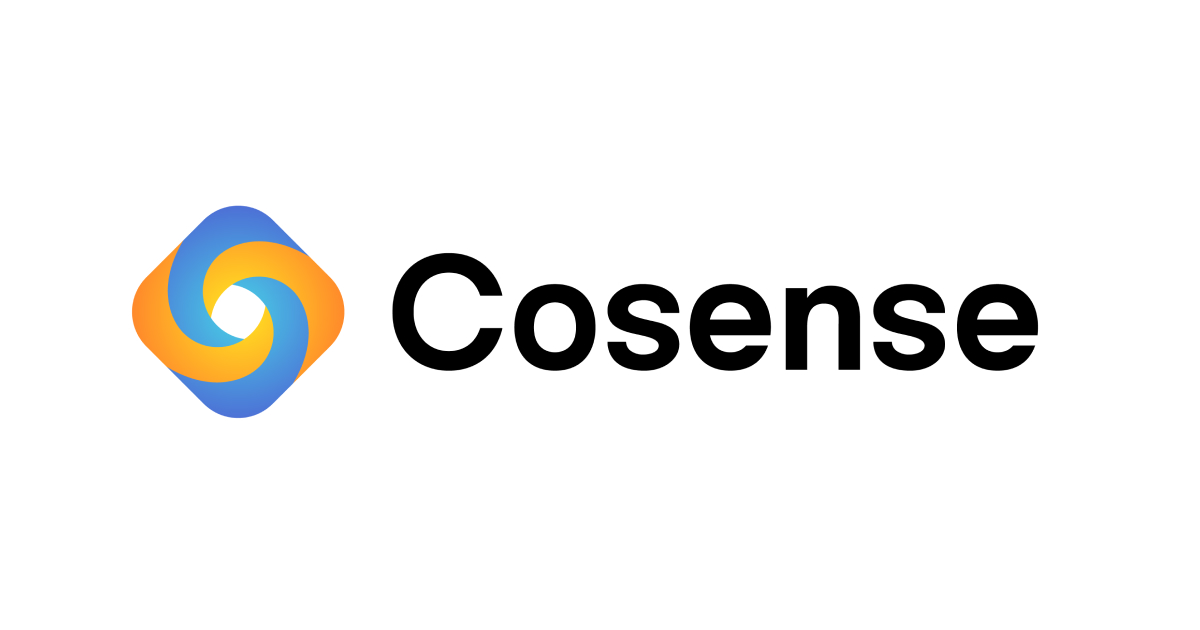
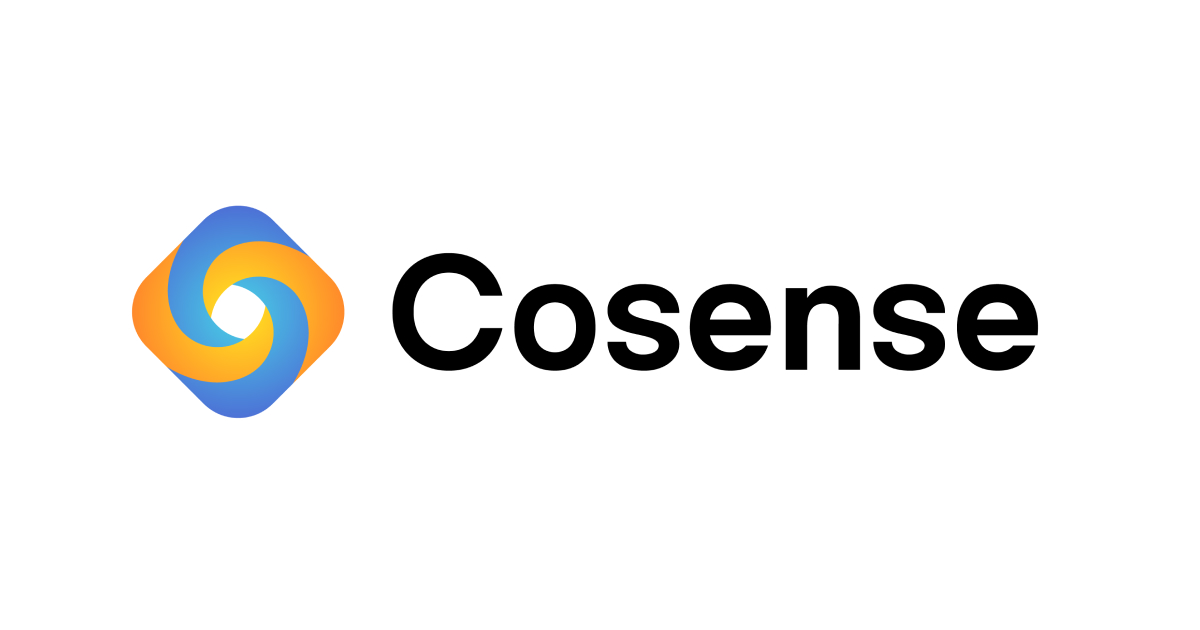


1. 名称変更がもたらした衝撃 – ビジネス色強化は「誤解」だったのか?


1-1. 「Helpfeel Cosense」が目指す世界 – プレスリリースに込められた真意
「Helpfeel Cosense」という新しい名前、そして「ナレッジイネーブルメントツール」というキャッチコピー。これらは、従来の「Scrapbox」に比べて、明らかにビジネス向けの印象を強めています。「Helpfeel Cosense(コセンス)」のプレスリリースでは、以下のような背景があったことが述べられています。
労働人口の減少を補う手法として、企業ではDXが進んでいますが、それに伴うデジタル化により生じる情報格差(ナレッジギャップ)は深刻さを増しています。
その上で、Cosenseの独自性として、以下の3つを挙げています。
① 高い検索性 ② 書きやすさ・読みやすさを追求したUI ③ チャット感覚のコミュニケーション
これらにより、「個人の暗黙知を組織のナレッジとして共有資産にしていく文化を日本に根付かせる」 ことを目指すとしています。確かに、企業におけるチーム利用を意識した方向性であることは伺えます。
しかし、Helpfeel社のエンジニアである寺本大輝氏の記事では、「Cosenseの方が、コンセプトに合った名前なのです」 と述べられています。彼によると、Cosenseという名前には、Co-sense, つまりcollaborationでmake sense! みたいな意味が込められているとのこと。つまり、複数人での利用を重視している一方で、この名称変更が、イコール個人ユーザー軽視というわけではない、ということがわかります。
1-2. 名称変更で深まったユーザーの不安 – その不安は今…?
名称変更は、多くの個人ユーザーに「自分たちはもうターゲットではないのか?」「Scrapboxの良さが失われてしまうのではないか?」という不安を抱かせました。
- ドメインの変更 (scrapbox.io から cosen.se へ):長年親しんだ「Scrapbox」という名前がドメインから消え、全く新しい「cosen.se」というドメインになった。
- サービス紹介ページの刷新:新しいサービス紹介ページは、ビジネス用語が多く並び、企業向けの課題解決を前面に押し出した内容となった。
これらの変更は、個人ユーザーに「使いづらくなるのでは?」という不安を抱かせるものでした。しかし、半年経った今、これらの不安は杞憂だったと言えるでしょう。なぜなら、Cosenseの根幹となる機能や使い心地は、Scrapbox時代から全く変わっていないからです。
2. 競合ツールとの比較で鮮明になる、Cosenseの独自性 – 個人利用における強みとは


2-1. 三者三様のナレッジ管理 – Notion、Obsidian、そしてCosense
ここで、NotionやObsidianといった、近年人気を集めている他のナレッジ管理ツールとの比較を通して、Cosenseの立ち位置を明確にしてみましょう。
- Notion:
- 特徴:データベース機能を備えた高機能ツール。
- Cosenseとの違い:Notionは多機能で、ページ単位での情報整理やリレーショナルデータベースによるデータの関連付けが得意。Cosenseは、Notionほど多機能ではありませんが、よりシンプルで、思考を妨げない「書きやすさ」に特化。また、ページという概念はNotionに近くありつつも、より粒度の粗い「ページ」によって、ページ内の情報整理のしやすさが特徴。
- Obsidian:
- 特徴:ローカル環境で動作するマークダウンエディタ。リンクによる知識のネットワーク化に強み。
- Cosenseとの違い:Obsidianは、ローカルファイルでの管理を軸に、マークダウン形式でメモを書き、双方向リンクによって知識を繋げていくツール。一方、Cosenseはリンクだけでなく、タグも活用して、ページ自体がカードのように振る舞うことによって緩やかに情報を繋げることができるのが特徴。
- Cosense (旧Scrapbox):
- 特徴:圧倒的な書きやすさと、リンクやタグによる緩やかな知識のネットワーク化が強み。
- 他ツールとの違い:Notionほど多機能ではなく、Obsidianほどリンク構築に特化しているわけでもありませんが、「書きやすさ」と「リンクやタグによる情報整理」のバランスが絶妙。
2-2. 個人ユーザーにとってのCosenseの価値 – 思考を後押しするツール
これらの比較から見えてくるのは、Cosenseが「個人の思考を後押しするツール」として独自のポジションを築いているということです。
Cosenseは、
- タグによる緩やかな情報の繋がり:Notionのデータベースほど厳密ではなく、Obsidianのリンク構築ほど手間もかからない、程よい粒度感。
- ページ内の見出しを意識した文章構成:ページ遷移を頻繁に行う必要が少ないため、思考が途切れにくい。
これらの特徴は、個人が思考を深め、知識を蓄積していく上で、とても有効。他のツールにはない、Cosenseならではの価値と言えるでしょう。
3. 静かなる進化 – 半年間のCosenseと個人ユーザーの現状、そしてこれから
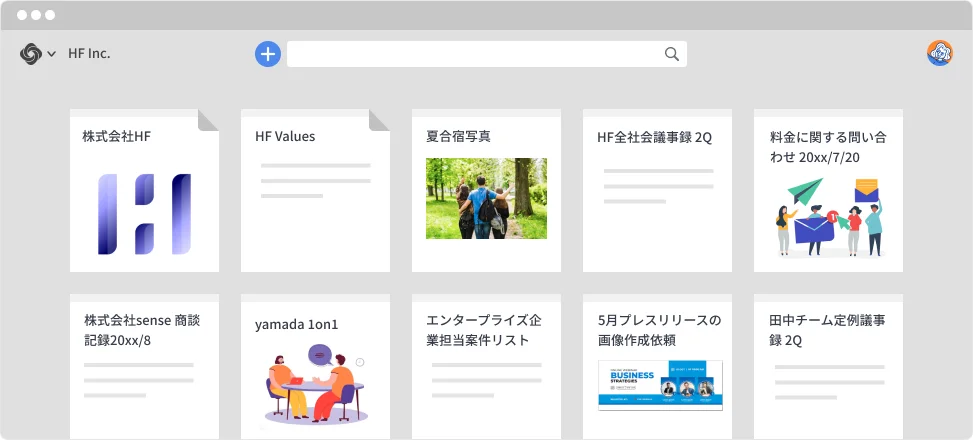
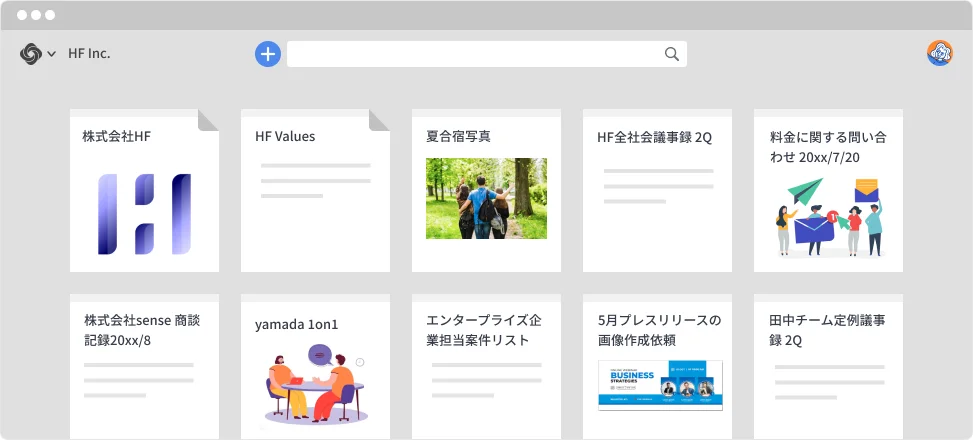
3-1. 企業向け展開は成長戦略 – 個人利用基盤は維持され、さらに成長中
では、名称変更から半年以上が経過した今、Cosenseを取り巻く状況はどう変化したのでしょうか?
この半年間、個人ユーザー向けの大きなアップデートや、積極的な情報発信は、あまり見られなかったように感じます。しかし、これはHelpfeel社が企業向けのサービス展開に注力していたためであり、個人ユーザーを軽視しているわけではないことが、先述の寺本氏の記事から読み取れます。
寺本氏は、Helpfeel社にとってCosenseは必要不可欠なツールであり、「Cosenseなしでは回りません」 と断言しています。さらに、「ちゃんと儲かってます」 とも。Cosenseの売上は、主に法人ユーザーの利用料金から生まれており、事業単体で既に黒字化、さらにHelpfeelとのシナジーもあって売上は伸び続けているとのこと。
つまり、表立った動きは少ないものの、個人利用の基盤はしっかりと維持されており、かつ、企業向け展開によって、より盤石な体制が整いつつあるのです。
3-2. ユーザーコミュニティの現状と今後 – 分散された情報共有とユーザーのこれから
現在、Cosenseには、Scrapbox時代のような、ユーザーが集う明確なコミュニティの場は存在していません。ユーザー間の主な交流の場は、X(旧Twitter)でのハッシュタグを用いた情報共有や、個人のブログでの活用事例の紹介などに限られ、特定の場所に集約されているわけではなく、分散している状況です。
しかし、このような状況だからこそ、今後ユーザーコミュニティがどのように形成されていくのか、注目したいところです。Helpfeel社の今後の企業戦略によって、ユーザーコミュニティのあり方も変わっていくことでしょう。ユーザーとしては、Helpfeel社が個人ユーザーの存在を今後も忘れないよう、願うばかりです。
4. Cosenseのこれからと個人ユーザー – 共に歩む道のり
4-1. Helpfeel社への期待 – 個人とビジネス、両輪での発展を願って
Helpfeel Cosenseは、個人利用の魅力を維持しつつ、企業向けのサービスとしても成長していくという、難しい舵取りを迫られています。この半年間は、企業向けの基盤固めに注力していた時期だったのでしょう。
今後は、
- 個人ユーザー向けの機能拡充や情報発信:NotionやObsidianに負けない、積極的な情報発信と、個人ユーザーのニーズに応える機能開発を期待します。
- 個人と企業、双方のユーザーが交流できるコミュニティの活性化:ユーザー同士が、Cosenseをより良く活用していくための知見を共有しあえる場の形成に期待します。
- Scrapbox時代から続く、オープンな開発の継続:ユーザーの声を積極的に取り入れ、ユーザーと共にサービスを成長させていく姿勢を、今後も継続してほしいと願っています。
など、個人とビジネス、両輪での発展を期待します。
4-2. 私たち個人ユーザーにできること – Cosenseと共に成長していくために
私たち個人ユーザーも、Cosenseのこれからに期待し、積極的に活用していくことで、その成長を支えていければと思います。
具体的には、
- Cosenseを使い続け、その良さを発信していくこと:ブログやSNSなどで、Cosenseの活用方法や魅力を発信していく。
- 他のユーザーと交流すること:他のユーザーの使用方法を知ることで、新たな活用方法が発見できるかもしれません。
- 要望やフィードバックを開発チームに届けること:ユーザーの声を開発チームに届けることで、Cosenseがより良いサービスへと進化していくための力となります。
など、できることはたくさんあります。
ビジネス色が強まった印象に惑わされず、Helpfeel Cosenseの本質的な価値を見極め、共に成長していけるよう、今後も使い続けていきたいですね。そして、その一助となるような情報発信を、このブログでも続けていきたいと思います。NotionやObsidianとは異なる、Cosenseならではの魅力を、一緒に育てていければ嬉しいです。


